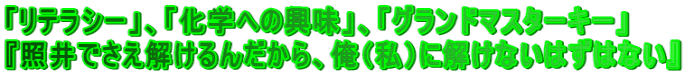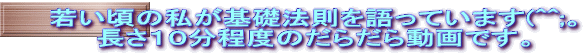| 前後期 |
講数 |
以下の『赤字文字』や『飾り文字』をクリックすると、詳しい説明や動画にジャンプします。 |
前
期 |
第
1
講 |
第1講の主目的のひとつは、化学結合について考えてみることでした(この赤字をクリックすると詳細な説明にジャンプします)。
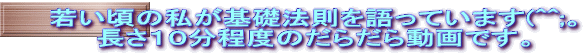 |
前
期 |
第
2
講 |
第2講では、まず、結合の種類に対応する結晶の種類と性質について整理し、次いで、金属結晶やイオン結晶を題材に、結晶ではいかに構成粒子が密に集合しているかや、結晶の安定性について考えてみることが目的でした(この赤字をクリックすると詳細な説明にジャンプします)。 |
前
期 |
第
3
講 |
第3講の目的は、酸塩基滴定を学ぶことにあります(この赤字をクリックすると詳細な説明にジャンプします)。3-1では、酢酸を水酸化ナトリウム水溶液で滴定する実験を通して、標準的な滴定操作の詳細を学習しました。3-2では、アンモニアの定量を通して、逆滴定という手法や、酸塩基滴定を利用することによって様々な定量(この問いの場合は窒素肥料中の硝酸アンモニウムの定量)ができることを学びました。3-3では、「炭酸ナトリウム水溶液」の滴定や、「水酸化ナトリウム、炭酸ナトリウム混合水溶液」の滴定を通して、二段滴定という手法や、そのパターン、反応式、反応が起こる順番、滴定曲線の形状、計算などについて学びました。 |
前
期 |
第
4
講 |
第4講の目的は、酸化還元滴定を学ぶことにあります(この赤字をクリックすると詳細な説明にジャンプします)。4-1では、幾つかの酸化還元反応について考えながら、過マンガン酸塩滴定を学習しました。4-2では、一気に、過マンガン酸塩滴定の応用ともいえる、COD(化学的酸素要求量)について考えてみました。4-3では、ヨウ素滴定を、酸化剤を定量する場合について学習しました。ちなみに、ヨウ素滴定の、還元剤を定量する場合についての演習をお望みならば、復習問題4-5がそれに該当します。また、ヨウ素滴定の応用ともいえる溶存酸素の定量についての演習をお望みならば、復習問題4-6にチャレンジしてみるとよいでしょう。
|
前
期 |
第
5
講 |
第5講の目的は、酸化還元反応を利用した電池・電気分解を学ぶことにあります(この赤字をクリックすると詳細な説明にジャンプします)。5-1では、電池の基本的な構成について考えながら、ダニエル電池を学習しました。5-2では、充電が可能な実用電池(二次電池)の代表例である、鉛蓄電池について考えてみました。5-3では、今後の期待される電池である、燃料電池について学習しました。さらに、5-4では、電気分解の基本について考えつつ、その化学工業への応用例であるイオン交換膜法や銅の電解製精錬について、簡単にではありますが考えてみました。ちなみに、電解槽の接続については学習しませんでしたが、詳細な説明のページの最後に記しましたし、演習をお望みならば、復習問題5-8にチャレンジしてみるとよいでしょう。
|
前
期 |
第
6、
7
講 |
第6,7講の目的は、気体の挙動を学ぶことにあります(この赤字をクリックすると詳細な説明にジャンプします)。
●第6講も、第7講も、気体の学習でしたが、第6講の前半まで(6-1)の学習の中心は『凝縮(液化)を考慮しない場合』で、第6講の後半から(6-3、7-1)の学習の中心は『凝縮(液化)を考慮する場合』でした。私の持論は、ボイルの法則、シャルルの法則、ボイル・シャルルの法則のいずれもが気体の状態方程式PV=nRT(ただし、P≦飽和蒸気圧)に含まれているので、『気体の状態方程式;PV=nRT(ただし、気体の圧力は飽和蒸気圧を超えない;P≦飽和蒸気圧)』を用いさえすれば、すべての気体の問題は解ける!というものです。よって、確実な得点を目指す時に意識すべき重要な事柄は、題材の違いを知ること(あらかじめ理解しておくこと)だと思います。
6-1は凝縮を考慮しない問題です。
6-3、7-1は混合気体について凝縮を考慮する問題です。混合気体について凝縮を考慮する問題には、P,V,Tの3つの変数のうちの一つを一定として考えさせる幾つかのパターンがあります。6-3が体積一定、7-1の問1、2が温度一定、7-1の問3,4が圧力(混合気体の全圧)一定というパターンです。
ちなみに、6-2は状態図の学習でしたが、ここでは、飽和蒸気圧についての理解を深めることを中心に、状態図のあれこれを考えてみました。
●以下の赤字をクリックすると、『気体の流れ』にジャンプできます。凝縮までを考慮する問題では、あらかじめ、P,V,Tの3つの変数のうちの一つを一定として考えさせる幾つかのパターンについて自分なりの理解をしておくことが有用です。ジャンプ先の『気体の流れ』にはそれも載せてありますので、気持ちに余裕がある方は、時間のあるときに軽く読んでおいて頂けると嬉しいです。 |
前
期 |
第
8
講
前
半 |
●第7講の7-3「気体の溶解度」も含めて、第8講は溶液がテーマです。ただし、7-3「気体の溶解度」、8-1「固体の溶解度」は、いわば、溶液を作ることについて学ぶ、8-2「蒸気圧降下と沸点上昇」、8-3「凝固点降下」、8-4「浸透圧」は溶液の性質について学ぶという内容でした。また、7-3,8-1では、目一杯溶かし込むという『飽和溶液』について扱ったわけですが、8-2~8-4では、溶媒の量にくらべて溶質の量が無視できるほど小さい『希薄溶液』について扱いました。前半と後半の学習内容の違いについて、自分なりに意識しておくと良いですね。
さて、7-3では気体の溶解度について学びました。気体の溶解度も、固体の溶解度と同様に温度によって変化しますが、同一の温度であっても、気体の溶解量はその圧力(分圧)に比例します。その比例関係の式(ヘンリーの法則)について、しっかりと把握しておきましょう。大半の気体の溶解量に関する問題は、ヘンリーの法則によって解くことができるわけですから。最後の問題(問3)については、気体の法則PV=nRTも用いますが、この問題では未知数が多く、ヘンリーの法則以外にも式を立てる必要があり、そこで、題材が密閉容器内の気体であることから気体の法則PV=nRTも用いた・・・ということに過ぎません。
8-1では固体の溶解度について学びました。固体の溶解度の問題の大半は、沈殿の量や飽和溶液にするための条件を問う問題です。沈殿は飽和溶液になったからこそ形成されるので、言い換えれば、固体の溶解度の問題の大半は、飽和溶液について考察する問題だということです。具体的には、飽和溶液における『溶媒と溶質の比例計算・・・①』または『溶液と溶質の比例計算・・・②』を行うということです。問1は沈殿に結晶水が含まれない問題、問2は沈殿に結晶水が含まれる問題ですが、どちらにせよ、上述の①または②の計算によって解くことができます。ただ、問1は題意を解釈しずらいので、ちょっとばかり解釈に手間がかかりそうですね。まずは、問2の解法をしっかりと身に付けましょう。
●復習;溶解度の学習の流れ |
前
期 |
第
8
講
後
半 |
8-2では蒸気圧降下という現象、蒸気圧降下を原因とする沸点上昇という現象、また、それらの現象の変化の大きさ(蒸気圧降下度、沸点上昇度)が質量モル濃度に比例することを学びました。8-3では、凝固点降下という現象、その現象の変化の大きさ(凝固点降下度)が質量モル濃度に比例すること、さらには、凝固点降下度を測定することで溶質の分子量(あるいは、会合度)を知ることが出来ることを学びました。8-4では、浸透という現象、その現象の大きさ(浸透圧)が(体積)モル濃度と絶対温度に比例すること、さらには、浸透圧を測定することで溶質の分子量を知ることが出来ることを学びました。凝固点降下度を求める実験(冷却曲線)や浸透圧を求める実験(液面差の圧力への換算)などについても、しっかりと押さえておきましょう。。
●復習[一部(U字管の片閉管や両閉管)は先取り];希薄溶液の学習の流れ |
前
期 |
第
9
講 |
●例えば、共有結合性の物質(有機化合物など)の結合エネルギーを知りたいと思うときには、
➀燃焼熱(または、水素化熱など)を測定する。
②『反応熱=生成物の生成熱の総和-反応物の生成熱の総和』であり、生成物である二酸化炭素(気体)と水(液体)の生成熱(それぞれ、黒鉛、水素の燃焼熱に等しい)は分かっているので(ちなみに、反応物の一つである酸素の生成熱は0)、測定した燃焼熱から目的の共有結合性の物質(有機化合物など)の生成熱を知ることができる。
③『反応熱=生成物の結合エネルギーの総和-反応物の結合エネルギーの総和』であるから、黒鉛の昇華熱を黒鉛のもつ全結合エネルーギーとおき、水素や酸素の結合エネルギーを既知とすれば、上記で求めた目的の有機化合物の生成熱から、目的の共有結合性の物質(有機化合物など)がもつ結合エネルギーの和を求めることができる。
●上記の流れを考えると、(少なくとも有機化合物を題材とする)熱化学の計算の主流は、
Ⅰ.燃焼熱(または、水素化熱)から生成熱を求める。または、その逆。
Ⅱ.生成熱から結合エネルギーを求める。または、その逆。
Ⅲ.燃焼熱から、ダイレクトに結合エネルギーを求める。または、その逆。
であろうと思われます。
●9-1の問題の内容をよくみてみると、すべて、上記のⅠ,Ⅱのいずれかです。そういったことに留意して復習すると、この問題がすっきりと整理できると思います。
問3・・・Ⅰ、問5・・・Ⅱ、問6・・・Ⅱ、問7・・・ⅠとⅡの連続 |
| ●9-2のような反応熱の測定を行う実験(熱量の計算)は、あれっ、中学理科じゃないの?とも思われる方がいらっしゃるかも知れませんが、上述のように、有機化合物の結合エネルギーを知ることなどに繋がりますので、とても重要な事柄です。実際に実験を行う場合などを想定して、データの読み取り方法なども確認しておきましょう。 |
| ●9-3ボルン-ハーバーサイクルというものがあります。イオン結晶の結合エネルギー(格子エネルギー、または、結晶エネルギーとも呼ぶ)を知りたいときには、ボルン-ハーバーサイクルが要となります。この赤字をクリックすると、ボルン-ハーバーサイクルの説明にジャンプします。お時間があるときに、気楽にお読み下さい。 |
|
前
期 |
第
10
講 |
●10-1は大きな流れを物語っています。表1にあるように、ある時刻における濃度を(適当な時間間隔ごとに)測定すれば、問2(1)にあるように、ある時間間隔における「平均濃度」、「平均速度」を算出することができ、さらには問2(2)にあるように、「平均濃度」と「平均速度」の関係式である「(反応)速度式」を導くことができます。また、「(反応)速度式」が導かれれば、実験データを代入することによって、「(反応)速度定数」を求めることができます。そして、これらの結果(とアレニウスの式)からは、問4にあるように活性化エネルギーを求めることができるというわけです。
●復習[アレーニウスの式や半減期などは発展項目];反応速度の学習の流れ
●10-2では、化学平衡の基本を学習しました。化学平衡の量的な関係は化学平衡の法則に従います。よって、化学平衡に関わる計算問題は、化学平衡の法則が基軸となります。問2は平衡定数を求める問題、問4は平衡時の量を求める問題、問5は反応の進む方向を判断する問題ですが、いずれも、化学平衡の法則が基軸であることに変わりはありません。また、問3は、平衡定数に関する問題ですが、(正反応と逆反応のどちらもが素反応的に進む場合)平衡定数は正反応の速度定数と逆反応の速度定数の比であることが示されています。
●10-4では、四酸化二窒素の解離平衡が題材となっていますが、これもまた、化学平衡の法則が基軸であることに変わりはありません。この問題にも、重要なテーマが潜んでいます。問3での解離度の算出に用いた式をじっくりと眺めてみて下さい。この式もまた、化学平衡の法則(からの変形)ですが、この式を検討すれば、平衡の移動方向を判断できます。すなわち、平衡の移動もまた、化学平衡の法則に支配されていると言えるでしょう。問3と問5は平衡定数に関する問題です。問3では(濃度)平衡定数と圧平衡定数の関係が、問5では平衡定数の温度依存性が問われています。
●10-3は、平衡移動の問題です。(1)~(3)は基本問題に過ぎません。(4)、(5)も本来は基本問題に過ぎないはずです。平衡の移動は、少なくとも「温度」または「濃度(または圧力)」が変化しなければ生じません。つまり、(4)、(5)はArを加えたことに気を奪われるのではなく、Arを加えたことによって「温度」または「濃度(または圧力)」が変化したか否かを吟味するに過ぎないのです。ちなみに、10-4の問4は、平衡の移動をグラフ的に考えさせる問題です。
●復習;化学平衡の法則の学習の流れ
|
前
期 |
第
11
講 |
●11-1は、最も代表的な電離平衡の問題です。ここでは、酢酸水溶液-水酸化ナトリウム水溶液滴定曲線を題材に、電離平衡について学習します。極めて頻出の題材なので、しっかりと理解するか、あるいは、せめて計算だけでも出来るように、きちんとした対策を取っておくことが必要です。酢酸水溶液-水酸化ナトリウム水溶液滴定曲線の学習は、「酢酸水溶液」、「酢酸-酢酸ナトリウム混合水溶液(緩衝液)」、「酢酸ナトリウム水溶液」の3テーマに分かれます。「酢酸水溶液」については、問1で扱います。「酢酸-酢酸ナトリウム混合水溶液(緩衝液)」については、問2で扱います。問2は、まず、(1)の理解に努めましょう。その理解なしには、(2)の理解は困難だと思われます。「酢酸ナトリウム水溶液」については、問3で扱います。ちなみに、『酢酸水溶液-水酸化ナトリウム水溶液滴定曲線』についての整理が完了すると、ほぼ同時に、『アンモニア水-塩酸滴定曲線』についての整理も完了することになります。これも、次の赤字(復習)に概略を載せておきます。
●復習;「酢酸-水酸化ナトリウム滴定曲線」の学習の流れ |
前
期 |
第
12
講 |
●12-1では、不均一系(固体と期待が共存している平衡状態)が題材であり、何やら難しげなイメージがありますが、『化学平衡に関わる計算問題は、化学平衡の法則が基軸となる』ことに変わりはありません。
●12-2では、分配平衡(化合物の分離)が題材であり、これもまた難しげなイメージがありますが、これもまた『化学平衡に関わる計算問題は、化学平衡の法則が基軸となる』ことに変わりはありません。化合物の分離を行う際のポイントについて知ることが出来る問題でもあり、興味をもって接して欲しいものです。
●12-3は、11講、12講の「化学平衡」という流れとは関係がありません。締めくくりの問題として楽しんで欲しいところですが、時間も不足していますので(^^;、駆け足になってしまうことをお許し下さい。この問題と同様の内容をもつ、よりシンプルな出題例(ここをクリックして下さい)を載せてい置きますので、復習に役立てて下さい。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|