| 酸塩基反応では、その終点の判定に、指示薬を用いました。しかし、酸塩基指示薬は、それ自身が酸や塩基ですから、多く加えることをしてはいけないなどの注意点があります。酸化還元反応では、その終点の判定に指示薬を使わなくても済みます(使わずに済むのは、それ自身の色が変化する指示薬のこと。ヨウ素の色の変化を補助するでんぷんなどは用いる)。酸化剤や還元剤には、反応に際して色の変化を伴うものが多々あり、その色の変化を利用すれば、終点の判定ができるからです。そのような観点から広く利用される酸化還元滴定の代表例のひとつが、過マンガン酸カリウムを用いた、過マンガン酸塩滴定です。 |
私達は、環境の汚染状況を、化学的な観点から測定する必要に迫られることがあります。そのような判定方法には、様々なものがありますが、その代表例の一つに、過マンガン酸塩滴定の応用例であるともいえるCOD(化学的酸素要求量)があります。これは、過マンガン酸塩滴定の学習の最終到達点ともいえるものですから、すぐにきちんと押さえておかなければならないというものではなく、気を楽にして向かってもらえば(あるいは、時期によっては、飛ばしてもらえば)良いと思います。注;上述の説明中のamolの過マンガン酸カリウムとbmolのシュウ酸は、過不足なく反応するように描かれている問題が主流です。 |
ヨウ素は、酸化剤の一つですが、酸化剤として働いた前後では色の変化があり、その色の変化はでんぷん水溶液を加えてある場合には(ヨウ素-でんぷん反応により)極めて明確です。よって、ヨウ素滴定は、終点の判定が容易で、過マンガン酸塩滴定と同様に広く用いられている酸化還元滴定です。ちなみに、「ヨウ素滴定」とは、要は「ヨウ素の量をチオ硫酸ナトリウム水溶液で滴定する」ということであり、求めたい物質の量をヨウ素に置き換えることができれば、求めたい物質の種類は問いません。すなわち、還元剤の定量はもとより、酸化剤の定量を行うことも可能です(ちなみに、出題頻度が高いのは後者の方です)。
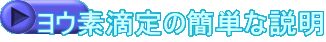 |