塩の液性は、ただ判別できるだけでなく、その理由(加水分解)もきちんと述べられるようにしておきましょう。中和滴定の終点の液性は中性とは限りません。中和点では塩が生成していますが、塩の液性は様々だからです。すなわち、塩の液性が判別できないと、中和点での液性を判定できません。中和点での液性を判定できないと、その滴定においてどのような指示薬を用いればよいのかを決定できなくなってしまいます。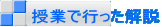
 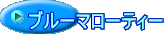 |
皆さんは、酢酸を水酸化ナトリウム水溶液を使って滴定する・・・という、標準的な滴定の手順を述べられますか?水酸化ナトリウム水溶液を用いるということは、水酸化ナトリウム水溶液を調製するということですが、同水溶液は正確な濃度には調製できません。よって、滴定に用いる前に、同水溶液を滴定するという手順が必要になります。この手順は、過マンガン酸カリウム水溶液を用いた酸化還元滴定などでも同様です。 |
さて、いよいよ、具体的な滴定に触れていきましょう。私達が納得しておかなければならない滴定は、左記の標準的な滴定ばかりではありません。たとえば、左記のような手法では、気体状態である酸や塩基、また、反応に時間がかかる固体の滴定(定量)はかなり困難です。
気体や固体の定量には、逆滴定が活躍します。逆滴定という用語はとらえようがありませんね。残余滴定(残ったものを滴定する)というイメージが納得しやすいかも知れません。 |